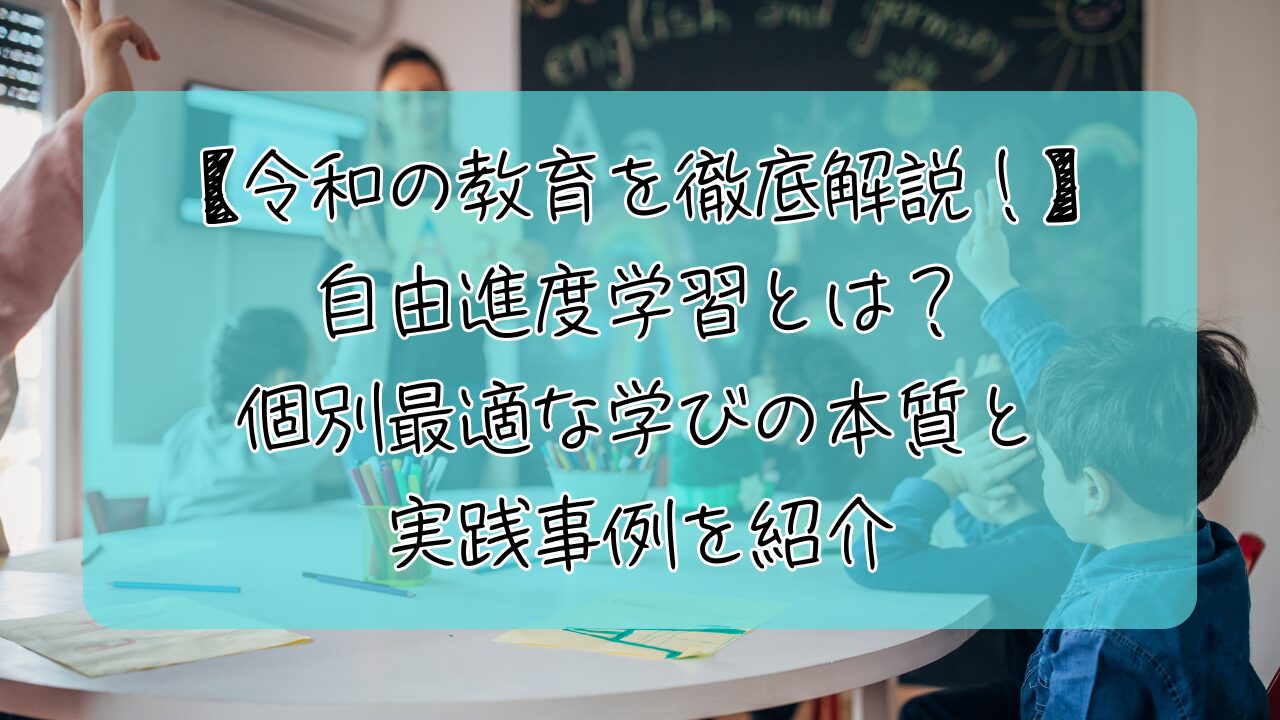
変わりゆく日本型学校教育
「みんな一緒に同じことを学ぶ」から「自分に合った学び方を選ぶ」時代へ。
2021年、中央教育審議会の答申で提起された「個別最適な学び」と「協働的な学び」。今、日本の教育が大きく変わろうとしています。
本記事では、奈須正裕氏の著書『個別最適な学びと協働的な学び』をもとに、「自由進度学習」という実践的なアプローチを中心に紹介しながら、実際に学校現場でどのように進められているのかを深掘りします。

保護者と教員向けに徹底解説して行きます!
 | 子どもが自ら学び出す! 自由進度学習のはじめかた [ 蓑手 章吾 ] 価格:2200円 |
自由進度学習とは?
自由進度学習とは、子どもたち一人ひとりが自分のペース・理解度・関心に応じて学びを進めるスタイルです。
教育改革の背景
かつての日本の学校教育は、すべての子どもに一定水準の教育を保障する「平等性」が評価されてきました。しかし、社会構造の変化により、「正解を覚える」学びでは対応できない時代に突入しています。

これからは「正解」ではなく「最適解」を学ぶ教育が求められているとも言えます。
奈須正裕氏が提唱する「学びの質の転換」
- 指導の個別化:学習進度・特性に応じて教材や方法を柔軟に調整
- 学習の個性化:子どもが自らの最適な学びを選び取る
- 協働的な学び:一人で黙々とではなく、仲間と共に思考を深め合う
教員向け:現場での自由進度学習の進め方
参考動画:カンテレNEWS
天童中部小学校の実践(抜粋)
① 自学自習
- 子どもたちだけで授業を進める形式
- 教師は不在、子どもが司会進行
- 成功のカギ:ルール設定、ICT活用、段階的な導入
② マイプラン学習
- 単元内自由進度型:1単元を子どもの計画で進める
- 「学習のてびき」の導入が鍵
- メタ認知力・学習効率の向上に寄与
③ フリースタイル学習
- 学ぶ内容すら子どもが決定
- 総合学習の中で取り組む
- 自己肯定感・キャリア形成にもつながる
中学校での実践例(パパ先生の現場より)
数学
- レベル別課題とグループ学習:自由に動いて協働的に解を探る
英語
- ビギナー/自習/アドバンスの3コース制
- ビギナー:先生や教材の動画を活用しながら学ぶ
- 自習:ワークに取り組みながら自由に質問・相談可
- アドバンス:英作文や英会話などアウトプット中心
- ALTによる添削・フィードバック付き
- 英検準2級〜2級レベルの導入も視野に
生徒の反応
- ビギナー:約20%/自習:約60%/アドバンス:約20%
- わからないことを「わからない」と言える雰囲気あり
- 英語が得意な生徒が意欲的に上位コースに挑戦
教員の負担軽減の工夫
- 単元の導入やまとめの時間に限定して実施することで、準備負担を抑える
- コースに応じた教材と進度表を事前に作成
- 活用できる動画教材・オンラインリソースをリストアップしておく

正直この取り組みを始めるにあたってはかなり準備が必要だと感じてしまいました。私の場合はまだ楽に始める方法をとれていますが…。動画では1授業に3週間かけたなんていう話もありました。
保護者向け:なぜ今「自由進度学習」なのか?
子どもたちが自立的に学ぶとは?
- 教師に言われたから学ぶのではなく、自ら問いを持ち、方法を考え、仲間と学び合う力が求められています。
- 自由進度学習は、「自分に合った学び方を模索する経験」そのものが成長につながる仕組みです。

自分で選んで学習できる子供はよく伸びます。そうした経験を意図的に学校で積ませることを目的としています。
おうちでできる支援
- 「どんな風に学んだの?」と聞いてみる
- プリントや作品を一緒に見ながら話を聞く
- 「自分に合った学び方ってあるのかな?」と問いかけてみる

何事もそうですが、学校の話題を家庭でしていただくことで、子供も自分に興味を持ってくれているという安心感があります。会話のネタにしてみてください。
まとめ:自由進度学習は“子どもを信じる学び”
自由進度学習の根底には、
「子どもはそもそも自立的で有能な学び手である」
という深い信念があります。
一斉指導の効率を補完するのではなく、これからの時代にふさわしい“学びの再構築”として、教員と保護者が手を取り合いながら支えていくことが重要です。

教員も生徒も、そして保護者も少し手探りの状態で進むことがあるかもしれません。それでも、学校を信頼していろんな新しい取り組みを見守っていただけたら幸いです。See you! 👋


コメント