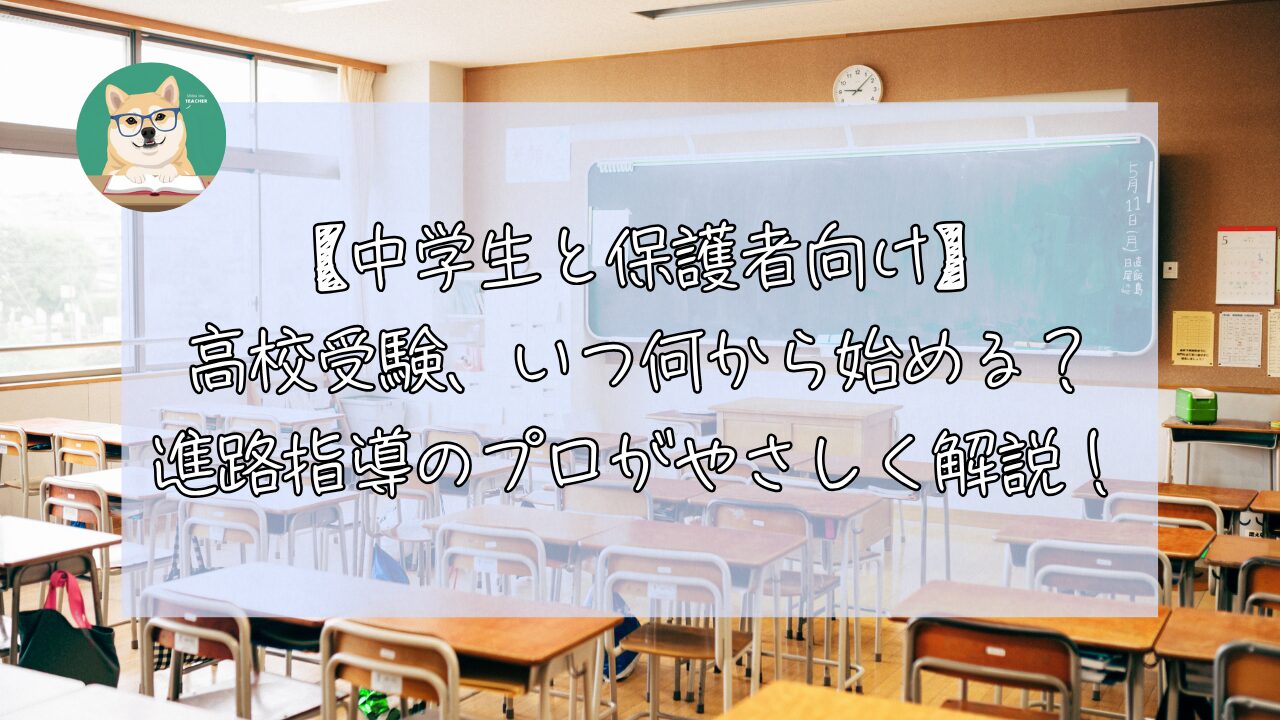
「うちの子、まだ受験なんて考えてなさそう…」「でも何か始めないと不安…」「もう中3だけで何から始めて良いかわからない…」
そんな風に感じている中学生の保護者の方へ。
受験に向けて最初にすべきことは、“難しい教材”でも、“受験情報の網羅”でもありません。
大切なのは「学年に応じた在すべきことをしっかり行う」こと。たったそれだけです。
今回は、進路指導の視点から、中学1〜3年生のうちにやっておくべき受験準備についてやさしく解説します。
そもそも高校受験って、どんな流れ?
高校受験には、大まかに次のようなステップがあります:
- 進路情報を集める(志望校探し)
- 学校の成績(内申点)を積み重ねる
- 模試や過去問で実力をつける
- 出願・受験
この中で中学1〜2年生の段階でできる最大の準備が、「内申点につながる学習習慣の確立」です。

内申点とは、中学校での教科の成績のことです。1〜5の数字が9教科分あり、それが3年間あるので、最大5×9×3=135となります。
一般的には110を超えてくると優秀だとされています。あくまで目安ですが…笑
そこに加えて、生徒会活動だったり、学級委員長、部活動の部長や専門委員会の委員長などの役職をやったり、英検3級以上などを持っていたりすると加点されるものになります。
加点材料は高校によって違うので、事前に確認すると良いと思います。
中1・中2でやるべき“たった一つのこと”
進路指導の現場で繰り返し伝えているのは、「まずは定期テストで点が取れる学習習慣をつける」ことです。
中学校では、成績の基礎になる「内申点(調査書点)」は、テストの点数だけでなく、提出物・授業態度・日々の取り組みが大きく影響します。
- ワークは毎回しっかり出す
- ノートや提出物をていねいに仕上げる
- わからない問題を放置せず質問する
この基本ができているだけで、定期テストの結果も内申点も確実に変わります。

こういう生徒は先生からの信頼も厚いのでいざというときに助けてもらえたりします。
学年別:進路活動のポイント
▷ 中学1年生
- まずは中学校の生活リズムに慣れる
- 家庭学習の「時間」と「場所」を決める
- テスト前に授業内容をまとめる(=復習する)習慣をつける
▷ 中学2年生
- 内申点に本格的に影響し始める学年
- 苦手教科を「そのまま」にしない勇気と努力
- 行きたい高校を1校だけでも一緒に探してみる
▷ 中学3年生
- 夏休み中に高校見学や体験授業に参加し、志望校を具体的に絞る
- 模試や過去問を通して実力を把握する
- 進路指導の現場でよく伝えている「テストの点数=切符の値段」という考え方を理解する
テストの点数=切符の値段の話
自分が持っているテストの点数は電車の切符代と同じだと考えるように指導しています。少ない金額の切符(=点数)だと、行ける駅(=高校)が限られてしまいます。しかし、金額の高い切符(=点数)であれば、終点まで行くことができます。もちろん途中で気に入った駅(=高校)があればそこで途中下車することもできます。
要するに、行きたい高校を自分で選択することが可能だということです。比較的、校則が緩い高校は学力が高い傾向にあります。服装や髪の毛の色も自由に選択できる学校も、学力が高い高校に多いです。今は、好きな進路先を選べるようにたくさん勉強してテストでたくさん点を取ることを目標に頑張ってみるといいと思います。
高校受験において、夏休み中に必ず高校見学を行うことをおすすめします。一度も行ったことのない高校を初めて受験するのは、想像以上にリスクが高いものです。雰囲気や通学手段、学校の方針など、自分の目で見て確かめることが大切です。
高校選びの際にまず優先すべきは「通いやすさ」です。毎日通う場所だからこそ、明らかに遠い高校やアクセスが悪い高校は避けた方がよいでしょう。どうしても行きたい高校がある場合は、それに見合った通学への覚悟が必要です。たとえば、朝1時間早く起きる、電車やバス通学に切り替えるなど、現実的な対策を考えておく必要があります。
それらの条件をクリアした上で、自分が学びたい学科があるか、頼れる先輩がいるか、文化祭などの学校行事が楽しそうかなどを判断材料にしていくと良いでしょう。
優先順位としては、通いやすさ → 自分の学びたい内容 → 学校の雰囲気という順番が理想的です。
高校では、中学校と違って欠席が続くと単位を取得できず、留年の可能性もあります。登校が難しいと感じる場合には、通信制高校や定時制高校も立派な選択肢です。自分のペースで学ぶことができ、働きながらでも学習を続けることができます。
最後に、「友達が行くから自分も」という理由だけで高校を決めるのは避けましょう。進学は自分の人生を左右する大切な選択です。多様な選択肢の中から、自分に合った高校を見つけてください。
保護者が今できるサポート3選
- 勉強する時間を確保してあげる
毎日30分でもOK。集中できる環境を整えることから。 - 「点数」より「過程」をほめる
「○点とれた?」ではなく「どこが頑張れた?」と聞いてみましょう。 - 子どもと一緒に“未来”を話す
「高校に行く意味」「将来なりたい姿」を軽く話すだけでも意識は変わります。
まとめ:今からでも遅くない。“習慣”が進路をつくる
高校受験は、「中3から本気を出せばいい」というものではありません。
むしろ、中1・中2のうちに「家庭学習の習慣」「学校での基本の積み重ね」ができている子が、受験で大きく伸びます。
完璧を求めなくてもいい。「できることを少しずつ積み重ねる」ことから、親子の進路活動は始まります。
“できることから始めてみる”、それがいちばんのスタートです。

今日の切符の話などは、私がよく進路集会などで生徒たちに伝えている内容です。何のために勉強するのか、勉強することの意味を感じにくくなった時にまた話をしてあげると効果的です。これからも一緒に頑張って行きましょう!See you! 👋

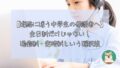
コメント