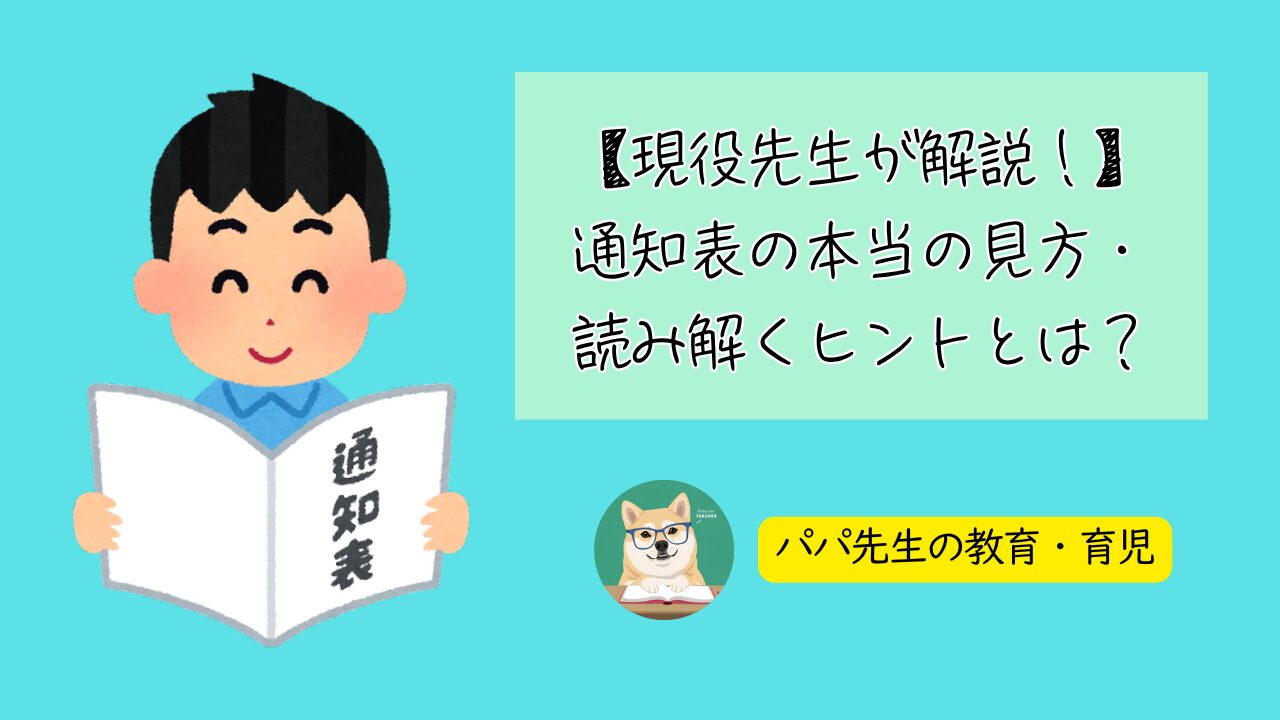
はじめに:通知表は「成績表」ではなく「成長記録」
夏休み前や学期末、子どもが手にする通知表。保護者の皆さんは、つい「成績だけ」に目がいってしまいませんか?
しかし、通知表はただの点数表ではありません。「どのような力が身についているか」「どこを伸ばせばよいか」という、子どもの学びの成長のヒントがたくさん詰まっているのです。

保護者にとっても子どもにとってもドキドキの通知表。通知表をきっかけに、今後ますます家族の会話が増えるようなアドバイスや見方を解説します。
評価の見方①:評定(1〜5)ではなく観点(A,B,C)に注目
通知表にある評価欄の多くは、テストの点数や授業中の活動や態度を反映させて評定だけでなく、観点別に「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」が記されています。

ほとんどの家庭では「5がいくつあったか」「1や2はないか」という数字に目が行きがちですが、今回はもう少し別な見方をしてみましょう。
例えば、こんな経験はありませんか?
- テストでは90点を取っているんだけど、評定は4だった。
- 小テストは毎回満点なのに評定が3だった。
このような現象が起こる背景には、評価は3つの観点で行なっている、という前提条件を知らないことが多くあります。
先ほどもお伝えしたとおり、評定とは
- 知識・技能
- 思考力・判断力・表現力
- 主体的に学びに向かう態度
この3つの観点で評価します。AAAなら5、AABなら4、ABB/BBB/BBCなら3、BCCなら2、CCCなら1といった感じです(※必ずそうなるというわけではありませんので誤解なきようお願いします)。
先ほどのケースだと、点数は取れているけど、もしかしたらパフォーマンステストであまり良い成績が取れていないのかもしれません。もしくは、授業中にあまり発表していないのかもしれません。
そんな時、保護者からは「もっと発表に参加しよう」「自分の考えをノートに書いてみよう」など、努力の方向を修正するチャンスにもなります。
努力は大切ですが、「どこで・どんな努力をするか」はもっと大切です。通知表は、そうした方向性を示してくれる“羅針盤”なのです。

努力の方向性を修正してあげるだけで、成績が伸びることは珍しくありません。ぜひどうして良いかわからない場合は先生に確認するといいでしょう。
評価の見方②:行動の記録は生活力のバロメーター
通知表の裏面や下部に記載されている「行動の記録」には、学校生活の様子が反映されています。さまざまな項目がありますが、今回私が特に注目してほしいのが「基本的生活習慣」の欄です。
ここでは、
- 身だしなみが整っている(だらしない服装をしていないか)
- 時間を守ってる
- 持ち物管理など、学力とは別の“生活力”が評価されています。
例えば、遅刻が多かったり、私語が多い生徒は、ここで評価が分かれることもあります。

「通知表はテストの結果だけじゃない」ことが、こうした欄からも見て取れますね。
評価の見方③:出欠の記録は家族の健康チェックにもなる
欠席・遅刻・早退の記録も、見逃せないポイントです。
もし保護者が知らない欠席や遅刻があれば、それは子どもと向き合う大切なサイン。
保護者の知らないところで、無断で欠席していたり、早退していたり、遅刻していたりなど、考えたくもないですが、そうした行動をする生徒も珍しくありません。
担任の先生に「すみません、確認なのですが…」と一声かけるだけで、状況がクリアになることもあります。
ここで大切なのは「先生に確認する」というスタンスを持つこと。
決して責めたり詰め寄ったりするのではなく、「一緒に子どもを支えたい」という気持ちを伝えることが大切です。
評価の見方④:生徒会や係活動の欄も要チェック!
保護者の中には、「うちの子、あまり学校のこと話してくれないんです」という声もよく聞きます。
しかし、通知表には「生徒会活動」「係活動」など、子どもが“こっそり”頑張っている姿が記録されていることも。
「え?副委員長やってたの?」なんて驚きの発見があるかもしれません。
そんな時は、過度に褒めすぎず「がんばってたんだね」と、静かに見守ってあげるくらいがちょうどいい距離感です。

子どもが親に言わないのは、単に恥ずかしいだけなこともあります。そんな子どもの気持ちを汲み取ってあげるのも、親の役目だと思います。
評価の見方⑤:所見欄は“先生からのラブレター”
最近では、所見欄を削減する学校も増えていますが、もし記載されているなら、先生が一人ひとりのことを本気で見て、想いを込めて書いてくれた文章です。
- いつも元気に挨拶をしてくれます
- 友達の気持ちを考えながら活動できました
- 友達と教室で仲良く過ごすことができました
- 時間を守って行動することができました
- 授業中に一生懸命手を上げて発表し、他の模範になりました
そんな一文に、先生の目に映るお子さんの姿が凝縮されています。ぜひ、家族で読んでほしいと思います。

所見欄は、ぜひ保護者の方には音読して欲しいレベルですね。笑
通知表をきっかけに「未来への会話」を始めよう
通知表は“子どもの成長の記録”であり、“保護者との対話のきっかけ”です。
良かったことも、これからの課題も、親子で一緒に確認してみてください。
「どうしてこうなったの?」ではなく、「どうしたらもっと良くなるかな?」と前向きな問いかけをしてみましょう。
子どもは、大人がどんな目で自分を見てくれているかを、敏感に感じ取っています。
親の声かけ一つで、子どものやる気も自己肯定感もぐんと高まります。
おわりに:通知表は、成長の“地図”です
通知表を「見る」のではなく、「読み解く」。
そして、その先にある「子どもとの対話」に繋げる。
そう考えれば、通知表はただの紙切れではなく、お子さんの未来への“道しるべ”になります。
成績に一喜一憂せず、ぜひ家族の成長ストーリーを語り合う機会にしてくださいね。

通知表をきっかけに、子どもや保護者が明るくなってくれたら私たちも作った甲斐があります。ぜひ、有効活用してくださいね!See you! 👋
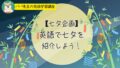
コメント